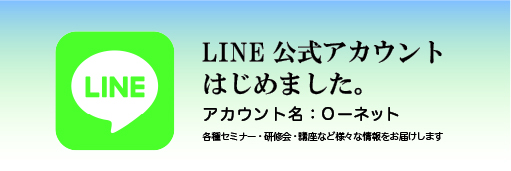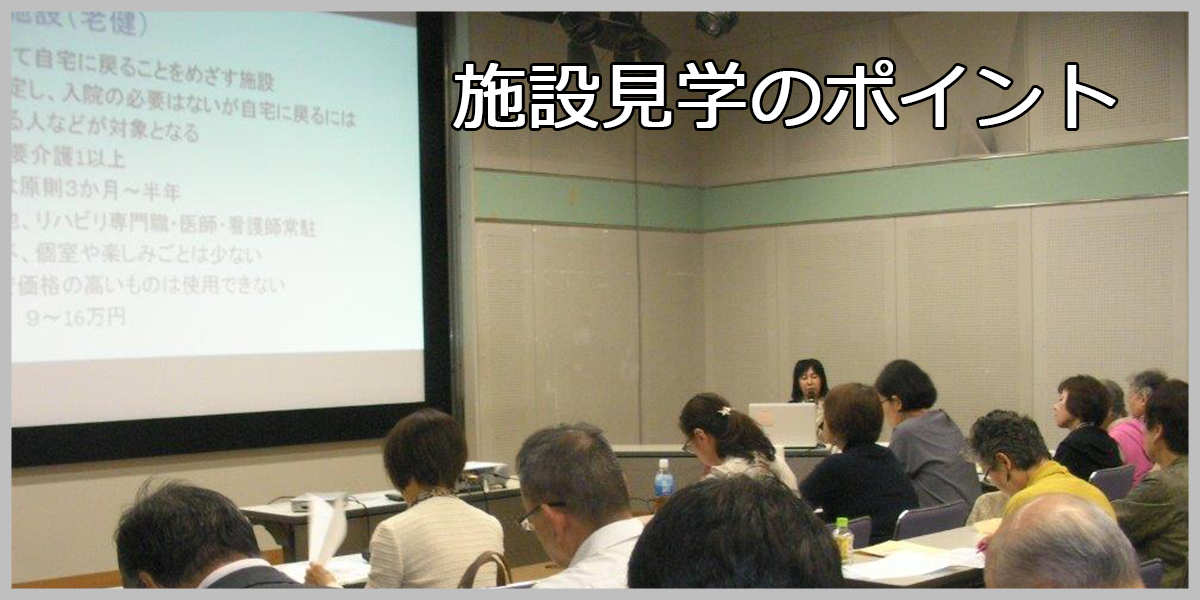介護現場の今とこれから

パネリストの皆さん。 右はコーディネーターの後藤由美子関西大学非常勤講師
6月10日、総会終了後第54回O-ネットセミナーを開催しました。人手不足が続くなか、介護現場では外国人介護士も増えつつあります。セミナーでは、最初に介護現場の現状と外国人受け入れの3つのルートについて後藤由美子・関西大学非常勤講師が説明。続いてEPA(経済連携協定)での受け入れを進めている濵田和則・晋栄福祉会理事長、今春より留学生の受け入れを始めた福留千佳・ライフサポート協会なごみ総合施設長が取り組み内容を紹介しました。後半は、外国人受け入れの課題や支援に詳しい後藤講師をコーディネーターにディスカッションを展開。参加者はオンブズマンや会員など67名でした。終了後のアンケートには「定着につながる制度となるよう国の努力も必要」「文化が違うので外国人による介護は無理と思っていたが、プラス面を活かし互いに切磋琢磨していきたい」など多くの感想が寄せられました。
日本語・国家試験に励む姿が日本人スタッフにも刺激に

濵田 和則 晋栄福祉会 理事長
09年度よりEPAでインドネシアの介護福祉士候補生を受け入れてきました。人材確保難を受け、早い段階から外国人の採用に踏み切り、経験を積んできました。現在、法人が運営する特養3か所で、国家試験に合格した介護福祉士9名と候補生10名、留学生6名が働いています。国別ではインドネシア人が21名、フィリピン人4名です。
EPAで来日するのは大半が現地で看護師の資格を取り、日本語能力も高い人が多いです。しかし通常より慎重に進め、食事介助は5か月目から、夜勤は国家資格取得後としています。
明るい性格の人が多いので利用者には好評です。既定の期間内では国家試験に合格できず帰国したものの、再挑戦し見事合格を果たしたガッツある人もいて、日本人スタッフも刺激を受けています。
学習や研修参加で業務を抜けたり、介護記録の表記間違いなどでサポートが必要だったりすることはありますが、日本人スタッフとの関係性も概して良好です。
いずれにしても介護業界の多国籍化・グローバル化は必至。団塊の世代が75歳以上となる2025年には夜勤職員の2割を外国人が担える体制を整えたいと思っています。
互いの国の事前理解が欠かせないことを痛感

福留 千佳 ライフサポート協会 なごみ総合施設長
今春初めて留学生を特養で受け入れました。介護の専門学校で学びながら、施設で週28時間を上限に働き実践力を培うプロジェクトの一環で、ベトナムの女子留学生2名を採用。入学前から働き始めましたが、短期間で課題もたくさん見えてきました。
まずこちらが困惑したのが無断欠勤や当日欠勤。「事前に連絡を」というと「給料が減るだけなのに、なぜ勝手に休んではいけないのか」と返ってきた。行方不明で心配していたら一時帰国だったこともありました。雑巾でテーブルを拭くなど生活習慣も違う。受け入れにあたって互いの国の文化・生活習慣の事前理解が不可欠だと痛感しました。
受け入れにあたって職員に研修する一方、日本の日常生活動作や接遇などをビジュアルで伝える留学生向けの独自マニュアルを作る必要性を感じました。留学生たちは、利用者には人気で明るくスキンシップも豊富。そうした特性・強みを活かすことも大切だったと思いました。
ふたりはその後「施設での受け入れ事業」を学校から外されました。現在はベトナムの男子留学生1名が働いています。定着につながるよう育成システムを整えていきます。
ディスカッション
定着促進には国の大胆な施策も必要
後藤●異文化理解は受け入れ施設の重要な課題ですね。
福留●留学生に「できる?」と聞いて「大丈夫」と答えても大丈夫ではないこともあります。米を地べたで研ぐ、箸先やスプーンのすくいの部分をもって受け渡しをするなどがあり、注意すると「日本人細かい」と言われたこともありました。相互理解の必要性とともに、「分かるように伝える力」を問われていることも身に染みて感じました。これからは、ベトナム料理教室を開くなど地域の人とも協同して留学生の孤立を防ぎ、楽しみを共有できる土壌を作っていかねばと思っています。
濵田●EPAの場合、最近では窓口である国際厚生事業団が候補生に日本の文化・習慣を教えてくれます。同時に、私どもでは相手国の生活習慣を理解するための研修を日本人スタッフに実施しています。とくにイスラム教を信仰するインドネシアの方の受け入れにあたっては、人権にも関わるだけに、1日5回の礼拝、ヘジャブの着用、禁忌の食べ物などイスラムの生活習慣を理解するよう努めています。施設内には礼拝できる場所も確保しています。職員採用であれサービス提供であれ、「多様性」はこれからのキーワード。それを育む柔軟な組織づくりが一段と求められると考えています。
後藤●学習や就労支援の他、生活面ではどのようなサポートが必要ですか。
濵田●居住環境の整備、結婚等の相談、宗教や食事の配慮など多岐に及びます。住居は法人が契約してUR住宅等を職員寮として提供、インターネットも法人契約で利用料のみ本人に請求しています。東南アジアでは20歳前後で結婚するためそうした相談も多い。母国に帰り、結婚後再来日するケースもあり、結婚相手の就職先を世話することもありました。
後藤●EPAの研修・就労期間中の一時帰国にはどのように対応しておられますか。
濵田●事前に打診があれば日本人同様、就業規則に則り、有休も使って1~2週間帰国できるようにしています。他施設では最長3日しか休めないところもあるようですが、一時帰国してリフレッシュしてもらったほうが定着につながると思います。
後藤●外国人の定着に向けて国の施策に望むこととは…。
濵田●EPAでは現在のところ、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国から毎年計1000人ほどしか受け入れられません。今後都市部では高齢者が急増するだけに留学生や技能実習生など他ルートの充実も望まれます。外国人の採用では学習支援に費用がかさみます。将来私たちの介護を支える人たちなのだから、外国人にも修学資金を適用してほしいですね。また能力が高く日本で継続的に働く意欲のある人をより多く採用していくためにも、福祉人材センターの国際版のような組織をつくり、そこが現地で日本語検定や一次面接を担い、人材を供給するような仕組みづくりが必要だと考えます。
福留●介護人材の確保と供給は「どんな社会をめざすのか」とも関わる重要な問題。単に自施設の労働力確保にとどまらず、介護を通じて自分たちが国と国との架け橋の一端を担っている。そんな大きな視野で考えることも必要です。
後藤●先行きの不透明感が強まるなか、国には思い切った施策も求められます。一方で介護の業務内容を整理し、個々の職員の力を考慮しながら業務を割り当てる機能分化の仕組みも今後求められていくのではないかと思います。いずれにしても介護の仕事はだれが担っても孤立しやすい面があります。情報を共有しながら対策を考え続けたいものです。