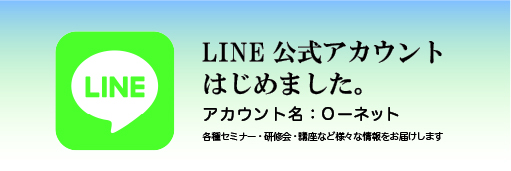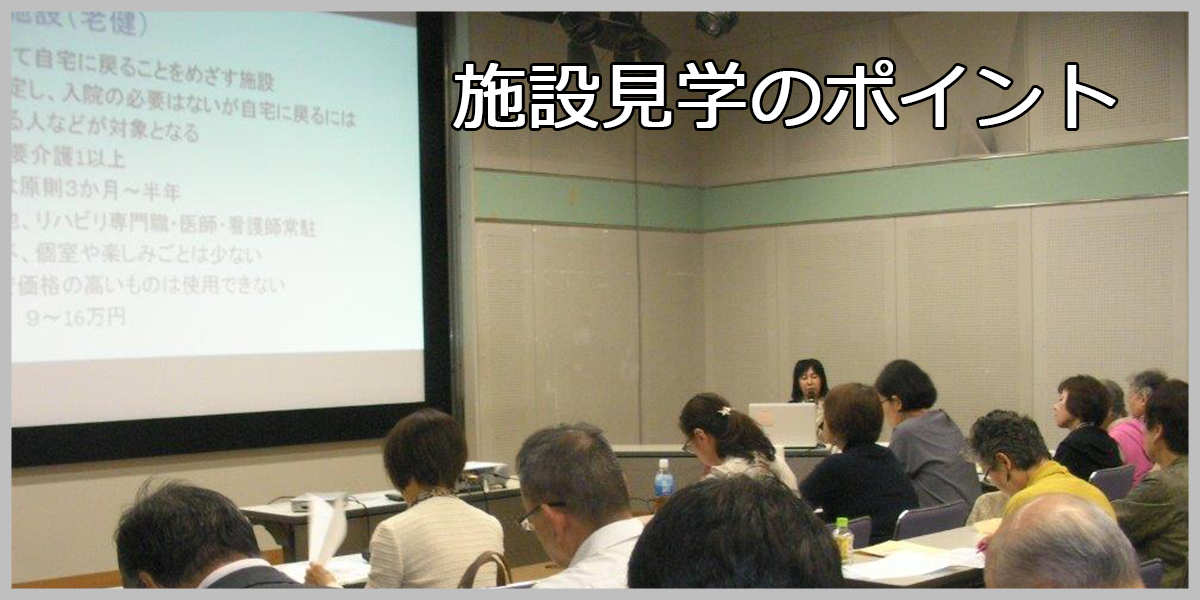1995年に介護保険制度をスタートさせたドイツ。「医療保険と同時に介護保険の被保険者となり、若年者も介護保険の適用を受ける」「家族が在宅介護を担う場合、サービス利用(現物給付)の代わりに介護手当(現金給付)を受給することもできる」など、日本の介護保険とは異なる点も多々あります。法改正によって2017年1月から施行された同制度には、認知症に配慮した要介護認定基準の見直しや家族介護者の支援拡大も盛り込まれました。4月1日の第56回O―ネットセミナー『ドイツの介護保険制度と介護事情』では、ドイツ人と結婚し長年同国で暮らしている渡辺・レグナー・嘉子さんを講師に招き、制度改正の内容やドイツで暮らす日本人の介護問題について伺いました。関係者を含む参加者は54名でした。

ドイツ在住者ならではの興味深い話を語るDejak名誉会長の渡辺・レグナ―・嘉子さん
異国で認知症が進む怖さ
語学教師で介護分野とは無縁でした。しかしある時、ドイツ語が堪能だった日本人女性が認知症を発症し、ドイツ語を忘れていく様を見て愕然としました。幼少期の頃しか思い出せず、日本の食べ物や生活習慣に強い思慕を抱く一方、ドイツの暮らしは受け入れにくくなる。ここに骨を埋めるだろう自分もドイツ語を忘れてしまったらどうなるのかと、不安に駆られました。
「お茶を飲んで慰めあっているだけではダメだ」と一念発起。2012年ドイツで暮らす日本人の老後に向き合い、介護のあり方を考えるDeJaK(デーヤック)友の会を設立しました。介護保険についての情報収集や認知症のことを学ぶとともに、ドイツの老人ホームで日本人が暮らしたとしても、日本語が話せて安心できる環境を整えようと、支援のための日本人ボランティアの養成や派遣を行っています。ここでは、この活動を通して知り得たドイツの介護事情についてお伝えします。
家族介護者の負担を軽減
昨年の制度改正では認知症に配慮した要介護認定基準と要介護度の見直しが行われました。認知症の発見率や対策では世界有数の実績がある日本に比べると「随分遅い」と思われるかもしれません。
ドイツの介護保険受給者は約300万人、認知症の人は約160万人。これまでは食事・衣服の着脱・歩行など基本動作の支援に重点が置かれ、要介護度も3段階でした。改正後は、認知能力・コミュニケーション能力、行動および心理状態、社会性なども判定の対象に。全6分野で評価・点数化され、その合計点で要介護1~5が決められます。
家族介護者への援助も拡充されました。要介護2~5であれば家族介護者がリフレッシュするための「介護負担軽減給付」を月最高125ユーロ(約1万2500円)まで給付。これを利用して州公認の有償ボランティアを頼めば週1~2回・数時間、休息や気分転換が可能になりました。
介護とは「文化」を担うもの
ドイツの高齢化率は21%以上。高齢者の貧困、介護・看護職やボランティアの不足も進んでいます。人口8280万人のうち920万人は外国人。介護職にはトルコ人や、ドイツ語圏の旧ドイツ領のポーランドやチェコの人が多いものの、外国人の介護問題もこれからの課題です。先述のように、外国で老後を迎える者にとって、言葉や食事・生活習慣の違い、これらは介護が必要になったとき、大きな問題になる。それだけに介護には出身国の生活・文化に応じた対応が望まれます。
介護とは、個々の国や個々人の「文化」を反映したものであり、尊重したものでなくてはならない、と思うのです。
我々の活動が、異国での介護のあり方を問う一つのモデルになればと思っています。