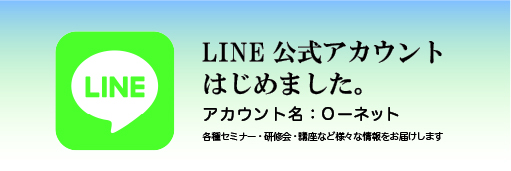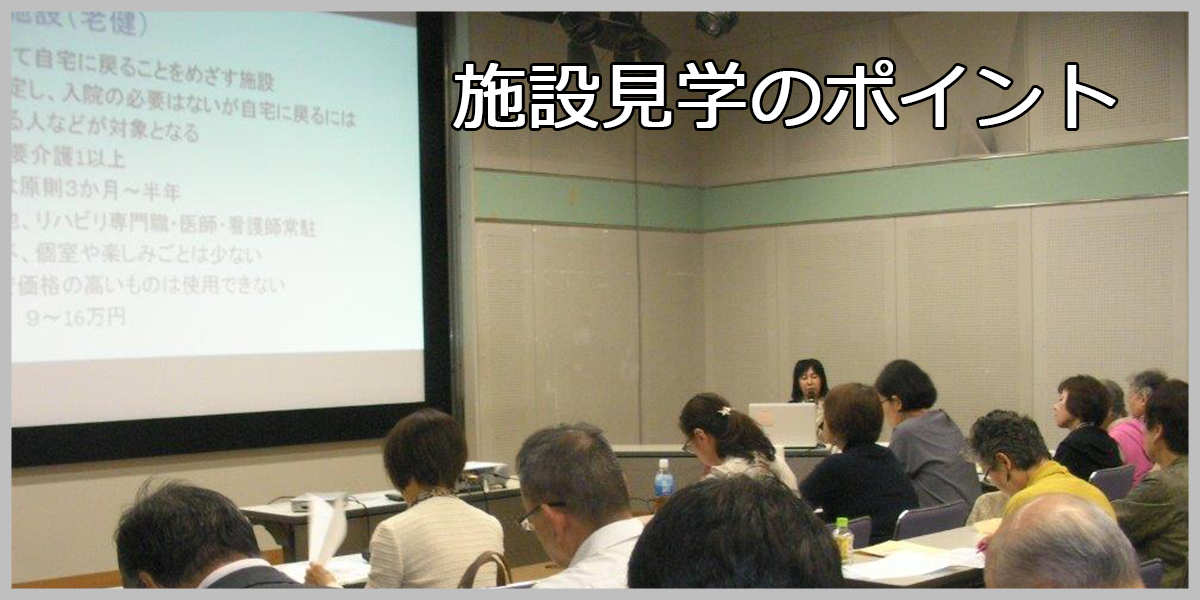介護リーダー研修で聴く力・話す力・見る力を高める

新崎国広・大阪教育大学教育学部教授。ソーシャルワーカー兼ボランティアコーディネーターとして働きながら社会福祉士資格取得後、教授に。
2018年10月13日と11月14日の2日間、介護施設のユニットリーダーやフロアリーダーを対象に、新崎国広大阪教育大学教授を講師に迎え職員研修「介護リーダーに求められるもの」を開催しました。41名の受講者がグループに別れ、リーダーの役割や課題、リーダーに求められるコミュニケーション力について学びました。
不安になるのは真剣に向き合っている証拠
今回のリーダー研修では、事前に受講者へアンケートを実施。リーダー共通の悩みは「人をまとめるのが難しい」でした。年齢もキャリアも、出身国さえ違うスタッフを指導するには、またスタッフに支持されるにはどうすればいい?
そんな課題を抱えたリーダーたちへの講師の最初のひと言は「皆さん、不安や悩みを持つのはエエことですよ。真剣に向き合っている証拠ですから」。

講師との後出しジャンケンで緊張がほぐれる会場
一人で抱え込まない助け上手・助けられ上手に
研修1日目に学んだのは「対人援助職のリーダーに必要なリーダーシップ」でした。
リーダーになると、スタッフの人材育成やチームのまとめ役など、職務の幅が一気に広がります。目の前の利用者の支援に加えて、新しい仕事も一人でこなそうとすると、経験不足から不安に陥ったり、思うようにはかどらず自信を失ったりしかねません。
リーダーには、全ての業務を自分だけで行おうとせず、周囲の人を信頼し任せることも必要です。周囲を巻き込みながら、組織やチームとしての「目標を掲げ、メンバーに伝えてまとめていく」のです。

課題をグループで話し合う。職場が違うメンバーでの意見交換は新鮮
メンバーの適材適所「PM理論」とは
目標を達成するのによいチーム作りに、コツはあるのでしょうか。
それが「PM理論」です。P型とは「目標を掲げ実現を目指すタイプ」。チームの方向性を示し、リーダーとしての自覚を持っています。M型とは「人を育てるタイプ」。メンバーの個々の良い点を探し共感をもって対応していきます。
受講者は各自、講師が作成したワークシートで、まず自分がどちらのタイプかをチェックしました。次にグループごとに集計すると、そのグループのタイプがみえてきました。
メンバー個々のP型・M型に善し悪しはありません。大切なのは、チームに双方のタイプがバランスよく構成されているかどうかです。例えば、自分がP型の場合、M型のスタッフがそばにいれば足りないところをフォローしてくれるでしょう。いなければ自分の中のM型を意識して出すようにすればチームはまとまりやすくなります。つまり、自分の強みはどこにあるのか自分を知ること、メンバー個々の能力や感情の動きを把握することが、リーダーシップにつながるのです。そしてメンバーを知るには日頃の雑談が大事。話し上手であり聴き上手なリーダーになりましょう。

教えるとは、ともに希望を語り合うこと
研修2日目の講義には、「対人支援のために倫理綱領を学ぶ」がありました。
「対人援助における三要素」を樹が育っていく過程になぞらえ、「1 大地に広がる根=価値・倫理、2 太い幹=専門知識、3 豊かに茂る葉=専門技術」と新崎講師。
いま介護の職場は、新人スタッフはもとよりリーダーにとっても厳しい状況です。最初の根の部分で仕事の価値を見い出せなくなったら…。例えれば、船が荒海に乗り出し行き先がわからなくなった状態です。そんな時に道標になる燈台が「倫理」です。
受講者は『介護福祉士の倫理綱領』を参考にしながら、講師が提示するさまざまな介護事例について、許せる範囲・許せない範囲をグループで話し合いました。施設は違っても、同じような場面に遭遇している受講者同士、話はつきません。
「教えるとは、ともに希望を語り合うこと」。「教える」を「育成」に変えれば、リーダーのスタッフへの向き合い方もみえてくるのではないでしょうか。