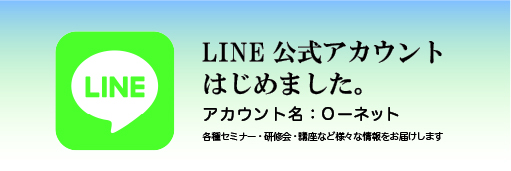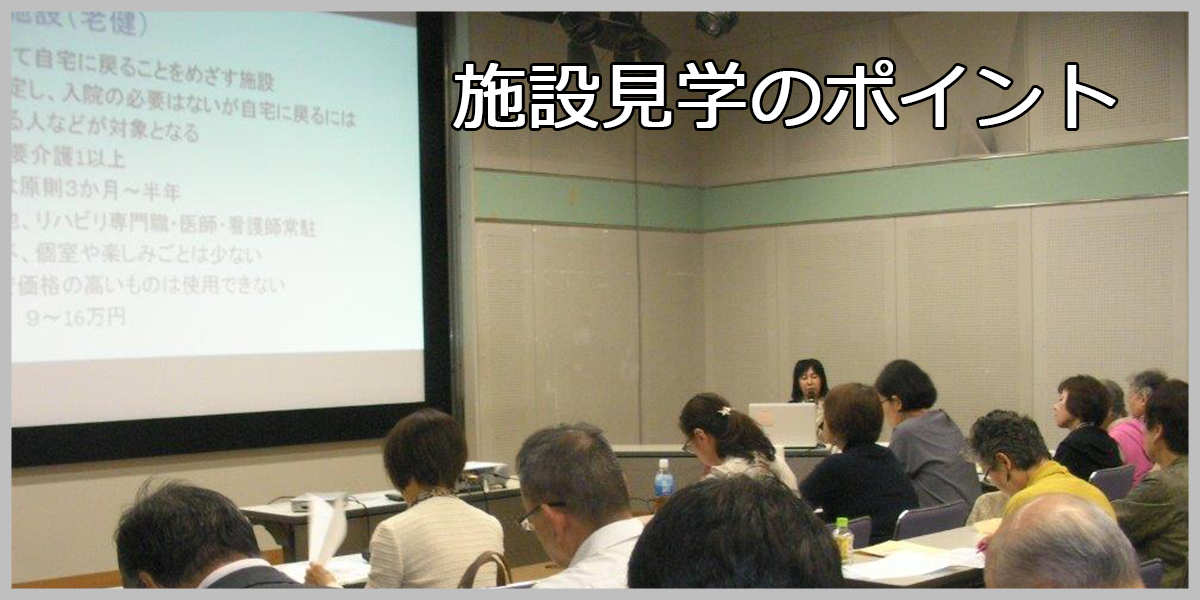川崎市の有料老人ホームで起きた職員による殺人事件は社会に衝撃を与えました。施設内虐待を防ぐため、O―ネットでは今年度も施設職員を対象に虐待防止研修を開きました。プログラムは、松宮良典弁護士による基調講演、自施設の取り組みを発表する実践報告(宝塚ちどり・本能)、桑野里美社会保険労務士による怒りをコントロールするアンガーマネジメント。参加者は特養や有料老人ホームで働く介護職員など62名。開講日までに定員を50名以上超える申し込みがあり、施設の危機感も強く感じられました。
あなたのケアは大丈夫?
高齢者虐待の背景と不適切ケアを防ぐための取り組みを考える
ふくろう法律事務所弁護士、介護支援専門員松宮 良典
【プロフィール】大学卒業後、京都の社会福祉法人に就職。ケアマネジャーや副施設長経験後、法科大学院に入学し、2006年の第1回新司法試験に合格。異色のキャリアを持つ弁護士として、介護問題を中心に活躍中。
人との関わりで大切なのは多元性と寛容性
高齢者虐待防止法の目的は高齢者の自分らしく安心して暮らす権利を守ることにあります。故意・過失に関わらず、客観的にみて本人の命・健康・生活が損なわれていれば「虐待」と認定されます。
では、なぜ認定する必要があるのでしょうか。虐待対応の目的は処罰ではなく、すみやかに虐待を解消し、高齢者が安心して暮らせるための「環境を整える」ことにあります。そのためにも対象者を明確にする必要があるのです。
虐待の類型には、身体的虐待・放任(ネグレクト)・心理的虐待・性的虐待・経済的虐待がありますが、筆頭に挙げられるのが暴行を加える身体的虐待です。厚労省の報告では20代の男性職員が最も起こしやすいことが統計でも表われています。まじめ過ぎてマニュアル通りにやろうとし、感情をコントロールする力が低い。そうしたことが要因と思われます。
例えば他人のパンを食べようとしていた高齢者に盗食防止から職員が足蹴りした事例―。人との関わりで一番大事なのは「多元性と寛容性」です。自分と異なる考え方や行動をとる人に対し、それを「認められるか」がカギとなる。他人の行動が生命・身体に危険を及ぼさないのであれば、少し逸脱していてもそれを認める。それが人権を守るポイントだと思います。
暴力は振るわないまでも、強制的にケアすることも身体的虐待や精神的虐待にあたります。例えば90代の高齢者が拒否しているにもかかわらず、1日1.5ℓの水分補給が必要とのことでお茶ゼリーを強要する。無理やり食べさせられて健康を維持するか、食べずに不健康になるかを決める自由は誰にあるのか…。食べたくないものを食べさせられるのは屈辱的です。
健康上の必要性の程度にもよりますが、法的には次のような点を考慮して判断します。
①お茶ゼリーを飲む目的は何か、②今やらないといけない必要性があるのか、③本人にとって不利益の少ない手段や方法を本当に選んでいるのか(お茶ゼリー以外の方法で飲みやすいものは提供できないのか)、④強要されることによる本人が被る不利益(精神的苦痛やその後の活動量の低下はないのか)。①②と③④を比較検討し、どちらが上回るかで判断していく必要があります。

仕事への誇りが虐待や事故防止につながる
表面化した虐待は氷山の一角にすぎません。その下には放置していると虐待につながりかねない不適切ケアが多数あるはずです。
とくに事故の中には、職員の不適切な介護によるものが少なくありません。大事なのは、危険性を予測して事故を未然に防ぐための判断力をもった職員を育てることです。
なぜ事故が起きたのか、そのとき職員はどう考えていたのか、どんなリスクがあるか確認して対応したのか…。事故後すみやかに、こうした点を一つひとつ丁寧に聴き取って確認し、原因を分析して皆で考えていかないと、職員の力量は上がりません。事故後は職員も反省しているので一番耳を傾けるときです。
事故を防ぐにはメリット・デメリットを常に考え、比較検討して対処できる力を培うことも大切です。この習慣をつけないと、いつまでたっても事故は減らないでしょう。
なお、苦情についてもそれがどんな意味を孕むのか、もっと丁寧に考える必要があります。例えば真夏にも関わらず冬布団を被っている人がいたとする。体温調整が難しい人であったとしても、冬布団のままというのはいかがなものか。単に夏布団にかえれば済む問題ではなく「ネグレクトになっていないか」といったことまで考えての対処が求められます。
苦情の意味をきちんと分析・評価すると、職員の意識も変わってきます。そういう点でも、オンブズマンなど外部の目による客観的な評価を受け止め、活かすことは、サービスの質向上、利用者の満足度アップにつながっていくと言えます。
いずれにしても、虐待防止には、利用者を敬う気持ちと、自分の仕事に対する誇りが不可欠です。利用者への敬意は、個々の高齢者の人生の具体的なエピソードを知り、共有することによって培われていくはずです。仕事への誇りは、利用者の状態が少しでも改善して喜ばれたり、頼りにされたり、誉められたりすることで育まれます。人の役に立っているというこの仕事の素晴らしさを実感して、今後もケアにあたっていただきたいと思います。

自施設の不適切ケアについて話し合う受講者の皆さん
2014年度「高齢者虐待調査」(厚労省/2016年2月発表)
★施設従事者による虐待件数…300件(前年度比35.7%増)。うち59件(約19.7%)は過去に指導あり
★施設の内訳…特養91件、有料老人ホーム67件、グループホーム40件、老健35件
★虐待の要因…①教育・知識・介護技術の問題184件(62.6%)②職員のストレスや感情コントロールの問題60件(20.4%)③職員の性格や資質の問題29件(9.9%)