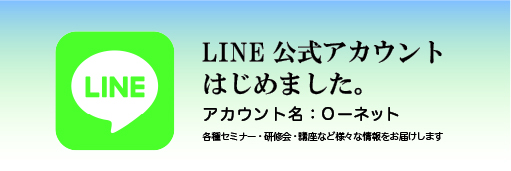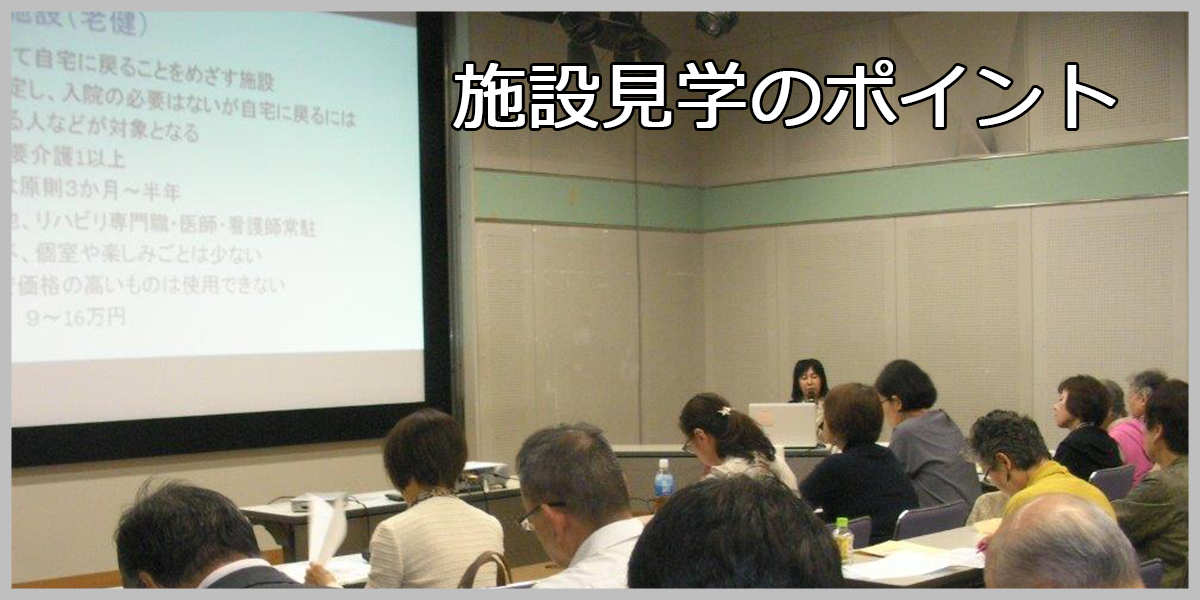O-ネットでは、定時総会終了後、第47回O-ネットセミナーを開催しました。
畑八重子・社会福祉法人みささぎ会認知症予防自立支援プロジェクト推進室長を講師に、参加者78名が軽度認知症障害(以下、MCIと略)について学びを深めました。

講師の畑八重子さん。
認知障害や認知症予防についても言及した。
厚労省の2012年の調査によると、認知症高齢者は462万人。MCIと呼ばれる認知症予備軍も400万人いると推計され、「65歳以上の4人に1人が認知症とその予備軍」と言われています。
MCIとは、健常と認知症の中間、グレーゾーンにある状態のこと。物忘れや約束の日時の間違いなどはあるものの、日常生活は可能です。ただし、MCIと診断された人のうち、約半数はその後発症し、年に12~15%の割合で認知症に移行するという調査報告もあります。認知症予備軍として注視されているのもそのためです。
早期発見・早期治療が大切と言われる昨今ですが、現在の認知症薬は症状の遅延が中心。治療薬や予防薬ではありません。そのため告知によってショックを受け、「これからどうやって生きていけばよいのか」と悩んでふさぎ込んだり、生活意欲が低下する場合も少なくありません。家族もどのように対応すればよいか分からず、家庭内が険悪になってしまう場合もあります。
「明確な解決策はありませんが、生活のありようを一緒に考えてくれる人が必要なことは間違いない。また、仕事など担っていた役割をやめてしまうのではなく、オープンにすることで周囲の理解を得て、活躍できる場を持つことが重要」と畑さんは話します。
講演ではNHKで放送された番組も視聴。失意にあったスコットランドの初期認知症の男性が、アルツハイマー協会の訪問担当者の働きかけで外出や趣味の写真を復活させていく様子や、リンクワーカーとの関わりを伝えています。
リンクワーカーとは、同国で2013年に制度化された専門職。診断直後から1年間集中的に当事者と関わり、生活上の課題や将来進行したときのケアなどを助言し、認知症とうまく付き合う方法を支援する役割を担っています。
「番組でも強調されていましたが、当事者の話を聴くことが何よりも大切。我々は認知症の人のことを分かっていないのだと知ることが重要です」
日本では気軽な相談窓口が少ないのが現状ですが、「まずは地域包括支援センターやケアマネジャーなどに相談してみては…。何か活路が見えてくるかもしれません」と畑さん。「もちろん日本版リンクワーカーの必要性についても声を上げていきたい」と結びました。