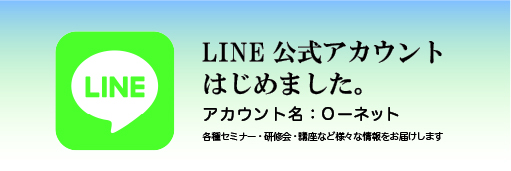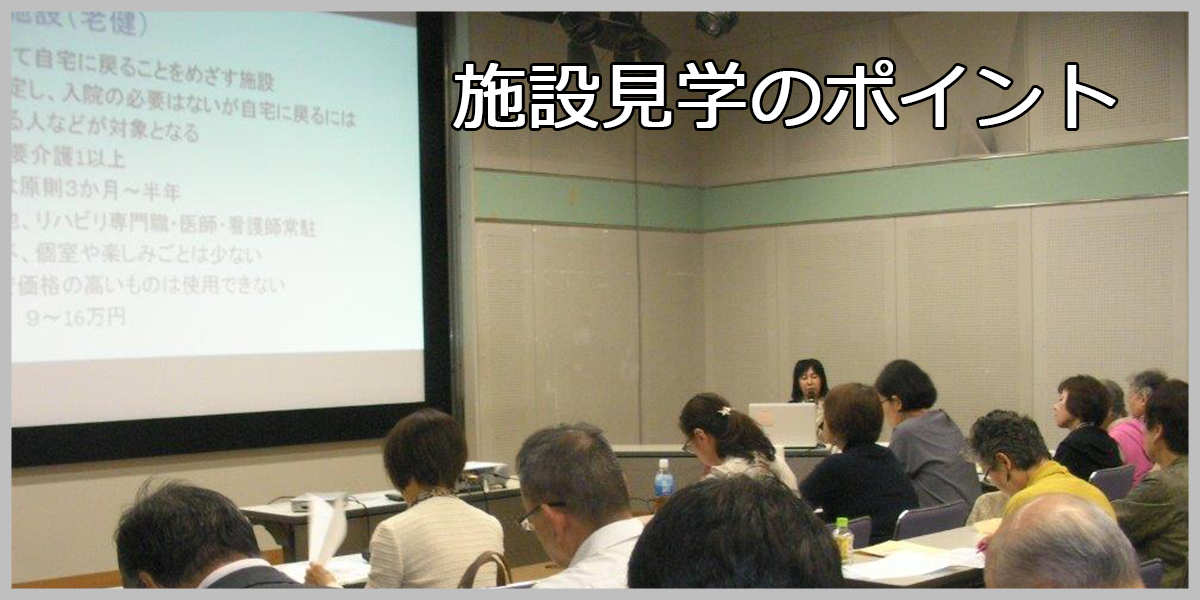認知症ケアや看取り、介護機器・ロボットの活用も
①認知症への理解とスキルの向上
特養で暮らす利用者の8割以上は、程度の差はあれ、認知症を患っています。そうした人々の不安や混乱を和らげ、安心して暮らせる居場所を提供するには、医療・介護の両面から、認知症に関する豊かな知識と観察・対応力を身につけていくことが、施設および職員に望まれます。
認知症への深い理解と対応は、利用者の自尊心を傷つけない態度や言葉づかいへの配慮となってあらわれ、不適切ケアや虐待の防止にもつながります。そのためにも、認知症ケアに対する知識や経験を常に職員間で共有し高め合うこと、そしてそのための仕組みづくりが、より一層望まれます。
②看取り介護の実施と充実
過度な医療処置や延命治療ではなく、穏やかに自然に最期を迎えたいと願う人は多くみられます。「終の棲家」である特養は、そうした死の看取りの場としての役割がますます望まれています。現在、看取りを実施している施設は特養の7割程度。まだまだ実績の少ない施設が多いのが現状ですが、家族・介護職・医療職がフラットな関係で看取る――。病院とは違った、そんな“介護施設モデル”の看取りが期待されています。
③介護機器・ロボットの上手な活用
座位や立位を取るのが難しい重度の利用者が増加するなか、移乗や移動介助は“人力による力任せの介護”だけでは限界があるのが実情です。介助方法がまずいと、利用者に苦痛や不快感を与えるだけでなく、ケガや事故につながります。また介護職員にとっても負担が大きく、肩や腰を痛める原因になりかねません。
ベッドから車椅子への移乗に役立つスライディングボードや、床走行式リフト、介護職員の腰に装着して負担軽減を図る介護ロボットなども最近では登場しています。職員の確保と定着を図るためにも、無理をせずに安心して働ける職場環境を早急に整えていくことが望まれます。