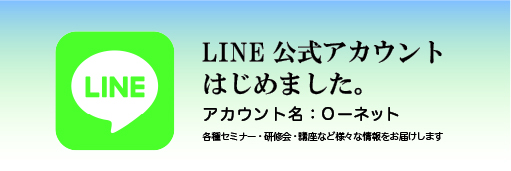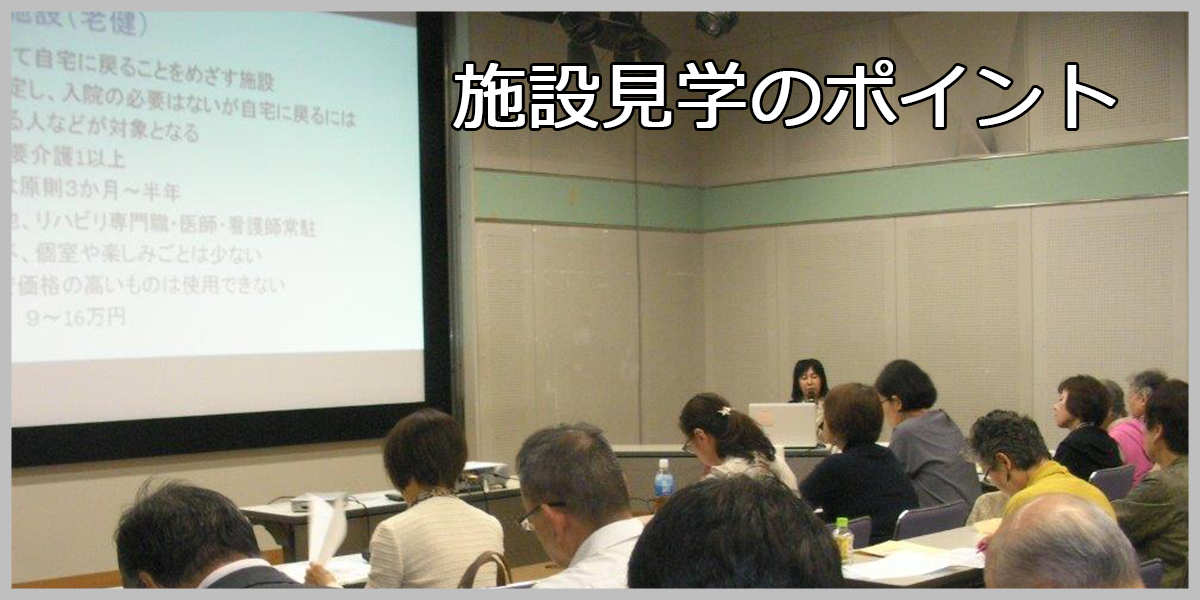特養入居で知っておきたいこと
食事は、施設で暮らす人々にとって数少ない楽しみの一つであり、「施設満足度」にも直結する重要な項目です。それだけに施設では、①「食べたい」という気持ちをいかに生みだし、②自分で食べられる(自力摂取)できるように食べやすい状況・環境を整えられるか、に心を配っています。
①「食べたい」気持ちを促すために
特養では昼食などに選択食を提供しているところがあります。2~3種類のメニューから選べる選択食は、自分の意思で選び決める「自己選択・自己決定」の機会にもつながります。
最近はソフト食を導入する施設も増えています。ソフト食とは、食材が舌で簡単に押しつぶせるほど柔らかく、飲み込みやすく工夫された食事形態。健康状態も考慮しながら噛む力や飲み込む力が弱い人に提供されます。普通の食事と変わらないような見た目と味のため、「食欲がわく」と喜ばれています。その他、ひな祭りのちらしずし・敬老会の祝い膳などの行事食、皆でホットケーキやお好み焼きなどをつくって食べる「料理レク」、外食や出前なども、食べる楽しさを引き出すための欠かせない取り組みです。
②食べやすい環境に配慮されているか
身体が不自由でうまく食べ物を口に運べない利用者のために、滑り止めの付いた器やトレイ、持ちやすいスプーンなど、食器類の工夫も欠かせません。
要介護度の高い利用者が多いだけに、食事どきはのど詰め(誤嚥)への注意も必要です。誤嚥を防ごうという意識の高い施設では、次の点にも意識して取り組んでいます。
(1)食事前の口腔体操 : 口やのどの体操で、飲み込みを助ける唾液の分泌を促します。
(2)食事時の姿勢への配慮 : テーブルの高さに対して座面が低くなり過ぎないようにします。
 「車椅子から椅子への座り替えを促す」「座高に合ったテーブルを用意する」などの工夫をして食べやすい環境を整えます。車椅子のアームサポートがテーブルの縁にあたって身体がテーブルから離れていたり、テーブルが高すぎて顎が上がった状態で食べている利用者を施設で見かけるときがありますが、危険です!
「車椅子から椅子への座り替えを促す」「座高に合ったテーブルを用意する」などの工夫をして食べやすい環境を整えます。車椅子のアームサポートがテーブルの縁にあたって身体がテーブルから離れていたり、テーブルが高すぎて顎が上がった状態で食べている利用者を施設で見かけるときがありますが、危険です!
③食事介助はココを見てみよう
(1)職員の声かけや話しかけがあるか
(2)食べ物を口に入れる速さや量は適切か
(3)職員が利用者の横に座り、1対1で食事介助を行っているか