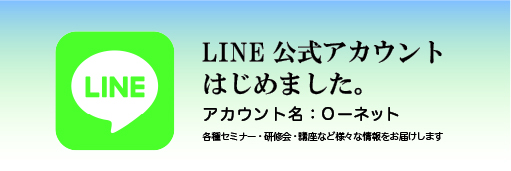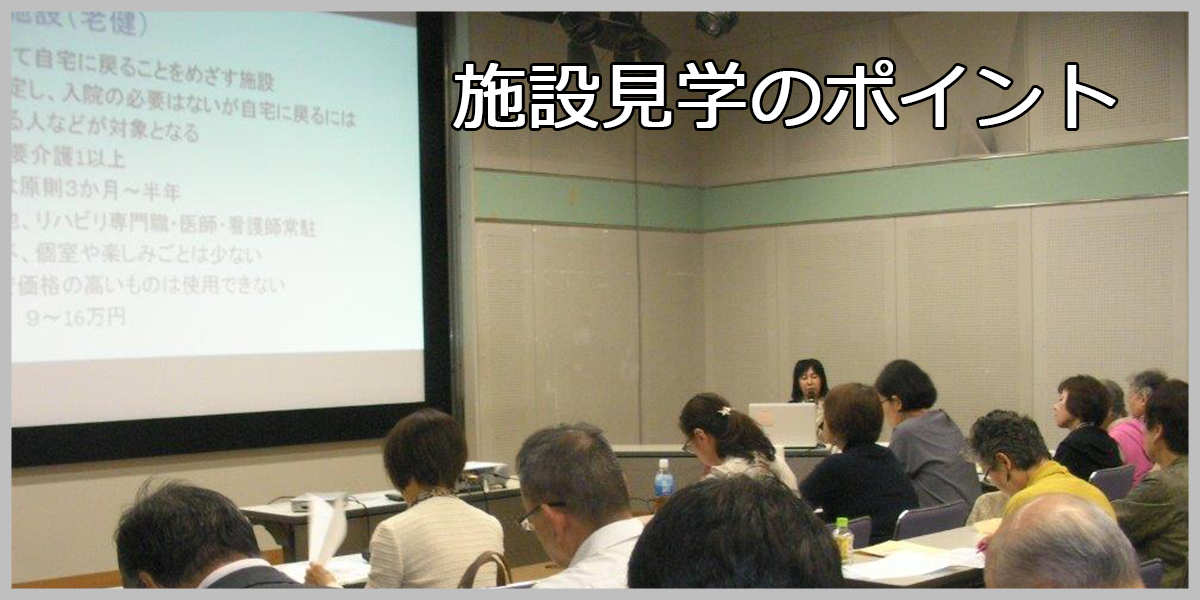夜間や急変時にも慌てず対応するために
12月6日ドーンセンターにて、山内恵美・白寿苑看護担当課長を講師に迎え、医療知識についての介護職員研修を行いました。
参加者 71名、 DVDで紹介される豊富な事例とともに嚥下や呼吸、痰、パーキンソン病、透析やバルーンカテーテルの管理など、高齢者を介護するうえで知っておきたいさまざまな医療知識について学びました。

高齢者に多いさまざまな症例について豊富な映像で分かりやすく解説
加齢に伴う身体・心理状態の特徴を知っておく
特養など施設に入居している利用者には、加齢による身体や心理状態の特徴がみられます。
まずこれらを知っておきましょう。
例えば「症状や経過がはっきりと現れない」。風邪を引いても発熱せず、肺炎なのに咳が出なかったりもします。
また「合併症や廃用症候群を起こしやすい」「回復に時間を要し慢性化する」「症状が急変しやすい」など。
認知機能や適応力が低下することから「意識障害やせん妄を起こしやすく」なったりもします。
大切なのは、疾病の症状を理解するだけでなく、それが利用者個々の生活にどんな影響を及ぼすのか。
何に困り、どう不都合なのかを考え、自立や自律を支援することです。
できない理由に気づきできるよう支援する
例えば食事で考えてみましょう。
食べるという行為が自立できれば、生活の中でできることも増えてきます。
箸やスプーンを使えれば鉛筆が持てます。
唾液がよく出てむせずに食べることができれば、大きな声を出したり歌を唄ったりしやすくなります。
そこで皆さん、食事が進まない利用者さんに「無理に食べさせる」ということをしていませんか。
介護は本来、指図するのではなく、自身で食べるよう支援するものです。
その利用者さんは何故、食べないのか、食べられないのかを探ることから始めてみましょう。
そうすると、嚥下の状態やタイミングを見計らう、スプーンに載せる量を減らす、とろみのお茶で飲み込みを助けるなど、個々に合う工夫がみえてきます。

個別性を重視し個々の困難を取り除く
次に高次脳機能障害がある利用者さんの食事について、実際の例を紹介します。
利用者さんは食べたい気持ちはあるのですが、道具の使い方が分からず、スプーンを逆さに持ってしまいます。
そして注意力障害のため、目に入るメニューすべてに手を出そうとし、更に食器から口までの距離が測れないので、食べ物を口まで運べません。
このように、ひと口に高次脳機能障害といっても、生活のどういう場面でどのように困るのかは、人によって異なります。介護ではそれを把握し、自立支援の方法を考えていかねばなりません.
この利用者さんには、小さめのおにぎり数個を入れた皿のみを提供してみました。すると、テーブル上の情報量が減ったのでおにぎりに集中できるようになりました。手でつかみやすいので道具は不要です。あとは、視線の先におにぎりを置き、声をかけておにぎりと口までの距離感を合わせるようにすると、自分で食べることができました。
ただし皆さん、支援はここで終わりではありません。
一旦は自立できた利用者さんも、重度化が進むと再びできなくなる可能性があります。
重要なのはそのとき、利用者さんが変化した状態を理解し、柔軟に支援方法を変えて、少しでも長く自立を持続することです。
とき 2019年12月6日(金)13時15分~16時40分
ところ ドーンセンター 5階 視聴覚スタジオ
大阪市中央区大手前1-3-49
地下鉄・京阪天満橋①番出口、東へ徒歩5分
定 員:70人(申込先着順)
対 象:介護施設・事業所で働く介護職員・看護職員など
講 師:山内恵美 看護師
特別養護老人ホーム白寿苑 看護担当課長
受講料:5,000円/人(O-ネット会員施設は3,000円)
プログラム
| 13時15分~13時15 分 受付 |
| 13時15分~13時30分 オープニング、開講挨拶 |
| 13時30分~16時40分 講義&演習「介護職が知っておきたい医療知識」 ~夜間や急変時にも慌てず対応するために~ |
| 16時30分~16時40分 アンケート記入、終了 |
お申込書
下記リンクをクリックして、募集要項および申込書をダウンロードしてください。
医療知識募集要項(PDF)
主催・問合せ先
介護保険市民オンブズマン機構大阪(O-ネット)職員研修実行委員会事務局
TEL06-6975-5221 FAX06-6975-5223
〒537-0025 大阪市東成区中道3-2-34 JAM大阪