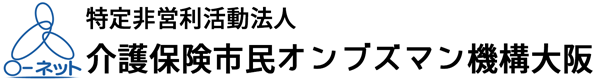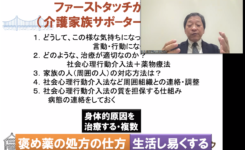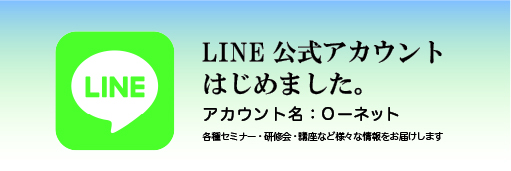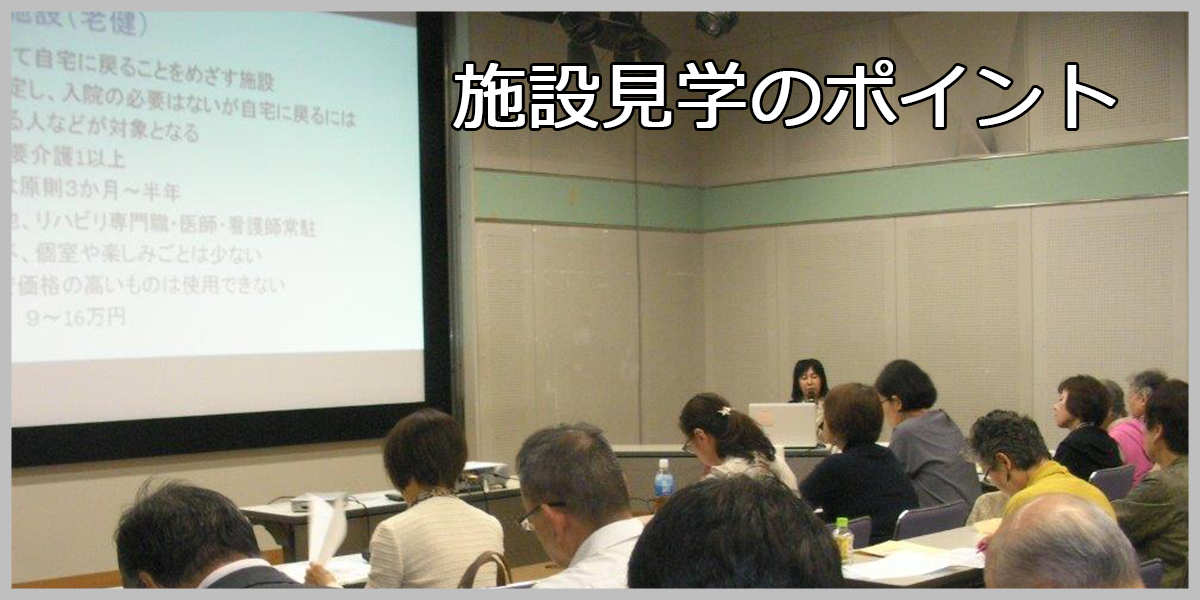要介護度の高い利用者の喜びにつなげるために
8月9日、ドーンセンターで施設職員研修『介護施設における楽しみの提供と工夫~要介護度の高い利用者の喜びにつなげるために~』(助成:日本社会福祉弘済会)を開催しました。
午前中は主に講義、午後は施設で活用できるさまざまなレクリエーションの提案や2施設による実践報告を実施。
「楽しみ」を軸に、考え方から具体的方法まで盛りだくさんなプログラムでした。施設職員26名の他、オンブズマン5名も参加。
水流寛二・桃山学院大学兼任講師の講義内容を紹介します。
レクリエーションは、自分らしさの発揮と生きる元気につなげる活動
- ゲームや歌だけがレクリエーションではない
 「レクリエーション」というと「集団で行う楽しみの活動」ととらえられがちです。
「レクリエーション」というと「集団で行う楽しみの活動」ととらえられがちです。
しかし、本来の意味は「社会生活における心身の疲れを休養や娯楽によって癒すこと」であり、「人が元来もっていたものを取り戻すこと」、すなわち「生きていく元気を取り戻し、再び作り直す活動」であると言えます。
そう考えると、生活を楽しみ快くするための一切の行為がレクリエーションであり、「生活のあらゆる場面にレクリエーションに結びつく要素がある」といっても過言ではありません。
レクリエーションは国家発揚のための手段として利用されたこともありました。
日本では戦後、意欲向上・生活向上と連動してレクリエーションが活発になり、労働者の福利厚生の一環として、あるいは青少年の健全育成のために、主にツール(手段)として用いられるようになりました。
そうしたなか昭和62年に社会福祉士・介護福祉士法が制定され、介護福祉士養成課程に「レクリエーション指導法」が登場。
しかし高齢分野での指導者が少なかったため青少年分野の指導者が講師を務め、子ども向けの内容を高齢者にも行うようになった。
ここに今日に至る「つまづき」がありました。
みんなで集まってゲームをしたり歌ったりということがレクリエーションだと誤解され定着してしまったのです。
- 日常の中で個々の利用者の快いものを考える
前述したように、レクリエーションとは「生活そのものを高め、楽しみを生み出すさまざまな営みを“総称するもの”」ですから、衣食住に関わること、つまり介護施設の日常において、いろんなことができる。例えば食空間を彩るランチョンマットや食器を個々の利用者に選んでもらう。
近隣への散歩で季節感や風物に触れる。「何が個々の利用者にとって快さにつながるのか」を、寄り添いながら見つけ出していく。
このことが何よりも大切です。
レクリエーションの究極の目的は「個人の主体的な活動を伸ばすこと」です。
人との関わりを豊かにする集団活動はレクリエーションの手段の一つではあるけれど、けっしてそれだけではない。
「個性を発揮する機会を生み出すこと」がレクリエーションのめざすものであることを忘れてはなりません。
最後に、介護職の人たちも、ストレスをため込まずに、自らを取り戻すためにレクリエーションを心がけてほしい。
それが新たなエネルギーを生み、利用者とのより良い関わりにつながっていくからです。
とき 2019年8月9日(金)午前10時~午後4時30分
ところ ドーンセンター 5階 視聴覚スタジオ
大阪市中央区大手前1-3-49
地下鉄・京阪天満橋①番出口、東へ徒歩5分
定 員:60人(申込先着順)
対 象:介護現場で働く介護職員・生活相談員など
受講料:5,000円/人(O-ネット会員施設は4,000円)
プログラム
| 10時~10時15 分 開講挨拶、オリエンテーション |
| 10時15分~10時45分 介護施設の「楽しみ」を見て~オンブズマンからみた気づきと提案~ 発表者/藤本委扶子・オンブズマン7期生 |
| 10時45分~11時45分 講義「生きる喜びにつながる“楽しみ”の提供とは」 講師/水流寛二・桃山学院大学兼任講師、 NPO法人キャンピズ代表 |
| 11時45分~12時 トライアルレポートの記入と提出について |
| 13時~15時 演習「楽しみを引き出すレクリエーションの実践」 講師/小山久子・日本アクティブコミュニティー協会公認講師 |
| 15時15分~16時15分 実践報告「施設の取り組みの実際と工夫」(2施設) |
| 16時15分~16時30分 アンケート記入、終了 |
研修の特徴:
①「レクリエーション介護士」養成講座の講師によるワークショップを開催します!
②NPOでハンディキャップのある人々の「楽しみ」を実践している講師による講義や、工夫ある取り組みを実施している施設の実践発表があります!
③研修で学んだことを活かし自施設の取り組みに挑戦していただきます。その内容をトライアルレポートとして提出していただき、受講者の方々の実践力を培います。各受講者のレポートはその後O-ネットの職員研修実行委員会で報告集としてまとめ、受講施設および受講者の方々にフィードバック。報告書を通して他施設の取り組み内容や工夫も学べます。
助成:日本社会福祉弘済会
主催・問合せ先
介護保険市民オンブズマン機構大阪(O-ネット)職員研修実行委員会事務局
TEL06-6975-5221 FAX06-6975-5223
〒537-0025 大阪市東成区中道3-2-34 JAM大阪