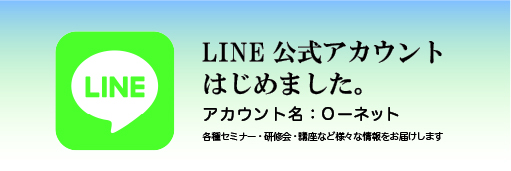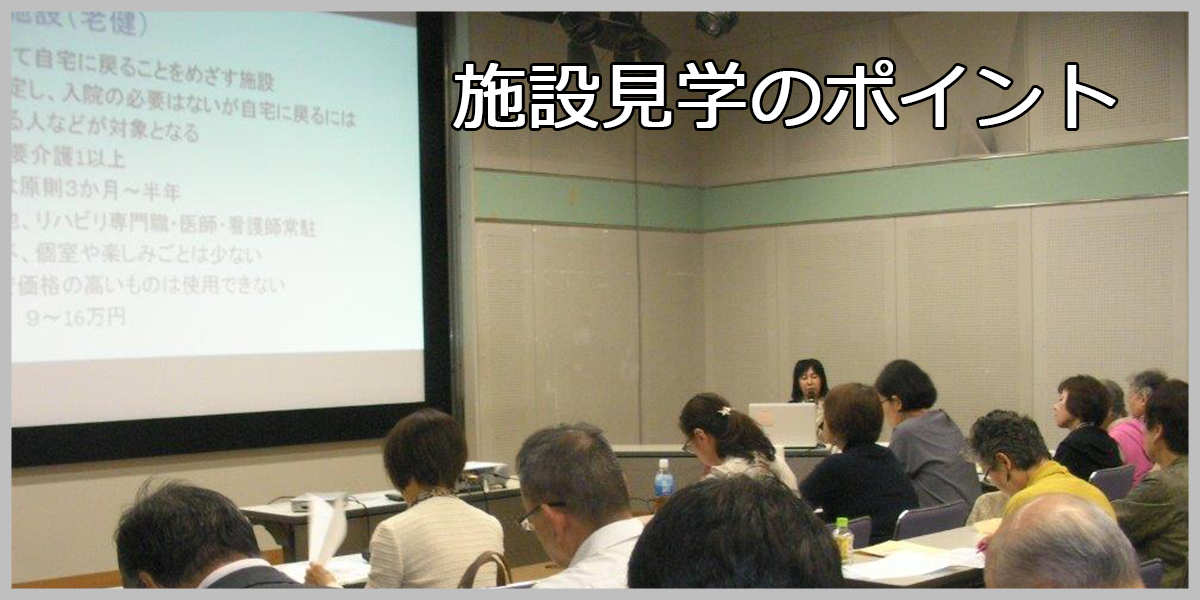第61 回O-ネットセミナー 会場参加・Zoomによるオンライン参加OK‼
『認知症の人の心の中はどうなっているのか?』【日本認知症ケア学会 後援】
 6月26日、第61回Oーネットセミナーをドーンセンターで開きました。認知症理解をテーマに佐藤眞一・大阪大学大学院教授が講演。会場とオンラインによるハイブリット型で行いました。認知症についての関心の高さに加え、緊急事態宣言の解除 ・ ワクチン接種の開始などが好影響を与え、 会場42名(スタッフ6名含む) 、オンライン82名の参加者多数となりました。
6月26日、第61回Oーネットセミナーをドーンセンターで開きました。認知症理解をテーマに佐藤眞一・大阪大学大学院教授が講演。会場とオンラインによるハイブリット型で行いました。認知症についての関心の高さに加え、緊急事態宣言の解除 ・ ワクチン接種の開始などが好影響を与え、 会場42名(スタッフ6名含む) 、オンライン82名の参加者多数となりました。

佐藤眞一・大阪大学大学院教授 専門は心理学。他の研究者と「日 常会話式認知機能評価CANDy」 を開発。『認知症の人の心の中は どうなっているのか︖』『マンガ 認知症』など著書多数。
「ケア」が「コントロール」にならないように
認知症のある人は3つの苦しみを抱えています。一つは「心がすれ違う苦しみ」です。例えば鍋を焦がした認知症の母親を「火事になったらどうする」と娘が叱責したところ、焦がしたことが問題と思い、母親が鍋を買いに行く…といったケースは、心がすれ違っている典型でしょう。
認知症の人は軽度の頃から社会的認知の低下が始まります。相手の表情から気持ちを察することが難しくなる。社会的規範が分からなかったり逸脱行動が出てきたりする場合もあります。「ケア」は思いやりから始まる行為ですが、社会的認知の低下による言動が出てくると、介護者も追い詰められ、相手を支配する言動となることが少なくない。それだけに介護者は「コントロール」になっていないか、常に留意が必要です。「言葉がすれ違う」ことも認知症の人の苦しみの一つです。記銘力の低下により、最近の出来事を話題にした会話が難しい。そのため一層会話の機会が減るという悪循環に陥りがちです。
調査によると、介護職員の業務時間の中で利用者との会話時間は1%ほど。そのうち「介助のための声かけ」が77%に上っています。いかに会話時間が少ないかが分かるでしょう。
3つめは「現実がすれ違う苦しみ」です。高齢者は視野が狭くなりがちですが、認知症の人の視野はより一層狭まり、情景全体の把握や人の顔を認識できない場合が多くあります。見えている一つのものに固執する傾向もあります。またレビー小体型認知症では花模様が小さな虫に見えるなど「幻視」と言って実際にないものが見えたりもします。
ともあれ、私たちにはこうした認知症の人の苦悩を理解することが何よりも求められます。そして生活環境や介護の仕方を工夫し、認知症があっても暮らしやすい社会にしていくことが、今後の課題と言えるでしょう。
「ボケたら何もわからなくなる」「すぐ忘れるので気楽でいい」——。
認知症についてのこんな誤解と偏見は少なくなってきているものの、皆無ではありません。
“自分が自分であること”の確かさが揺らぎ、大きな不安を抱えながら日々過ごしている認知症の人たち…。
日常会話を通して認知症の人の状況を理解し会話を増やすためのツール『CANDy』の共同開発者の一人・佐藤眞一さんを講師に、研究成果に基づきながら、認知症の人の「コミュニケーションの特徴」や「見ている世界」、そして「孤独や苦悩」を知ることを通して、心の読み解き方に迫ります。
認知症の人をよりよく理解することで、家族の接し方や介護も変わる――。心理学の視点をもとに、認知症について改めて学び考えます。
会場またはZoomによるオンラインでご参加可能な「ハイブリッド型セミナー」です!
日時:2021年6月26日(土)14時30分~16時
会場:ドーンセンター5階・大会議室2
講師:佐藤眞一・大阪大学大学院人間科学研究科教授
専門は老年行動学、老年心理学、生涯発達心理学。今回のセミナーのタイトルでもある『認知症の人の心の中はどうなっているのか?』をはじめ、『ご老人は謎だらけ 老年行動学が解き明かす』『認知症「不可解な行動」には理由がある』など著書多数。昨年6月刊行の『マンガ 認知症』も好評で新聞の書評欄でも紹介されている。
定員:60人 ※会場参加30名(申込先着順終了)、オンライン参加30名(申込締切6月20日)(受付終了)
対象:認知症ケアに関心のある人々・家族、施設関係者など
参加費:一般 1,000円、会員500円
申込方法:下記の手順でお願いします(受付終了)
(1)Web でお申し込みの場合
下記申込フォームに必要事項を入力し、送信してください
<申込フォーム>
(2)FAX・郵便でお申し込みの場合(受付終了)
下記の申込書をダウンロードし、事務局へお送りください。
<お申込書>
下記リンクをクリックして、チラシ裏面申込書をダウンロードしてください。
第61回O-ネットセミナーチラシ
(3)電話でお申し込みの場合(受付終了)
水・土・日・祝を除く10:00 ~ 17:00 にお願いします。
主催・問合せ先:
介護保険市民オンブズマン機構大阪(O-ネット) 職員研修実行委員会事務局
TEL06-6975-5221 FAX06-6975-5223
〒537-0025 大阪市東成区中道3-2-34
後援:日本認知症ケア学会